「マグマの海」が「海水の海」に変わり、シノアバクテリアが登場します。
シノアバクテリアは、気体としての酸素を、海水中へ、大気中へ、充満させます。
さらに、オゾン層を創出して、動植物が海中から陸上へ生息圏を広げる条件を整えます。
5億年前ごろから、コケ植物が海中から陸上へ進出します。
4億5000万年前ごろから、シダ植物が海中から陸上へ進出します。
4億年前ごろから、昆虫が海中から陸上へ進出します。
同じころ半水性で半陸性のハイギョが登場しますが、脊椎動物の祖である魚類は、一部が淡水域へ進出したものの、大半は海中に止まらざるを得ませんでした。
3億6000万年前ごろ、両生類が登場します。
3億3000万年前ごろ、爬虫類が登場します。
2億4000万年前ごろ、哺乳類が登場します。
1億5000万年前ごろ、鳥類が登場します。
脊椎動物は、両生類・爬虫類・哺乳類・鳥類へ進化しながら、生息圏を海中から陸上へ大空へと拡大させました。
にもかかわらず、魚類は依然として海水中ないし淡水中に止まらざるをえませんでした。
そこで浮世絵師の歌川広重が、5億年以上もの間、海水中や淡水中から大空を見上げ続けてきた、魚類の想いに応えたのかもしれません。
『名所江戸百景 水道橋駿河台』では、漆黒のコイが天頂へ向かって羽ばたいているように見えます。
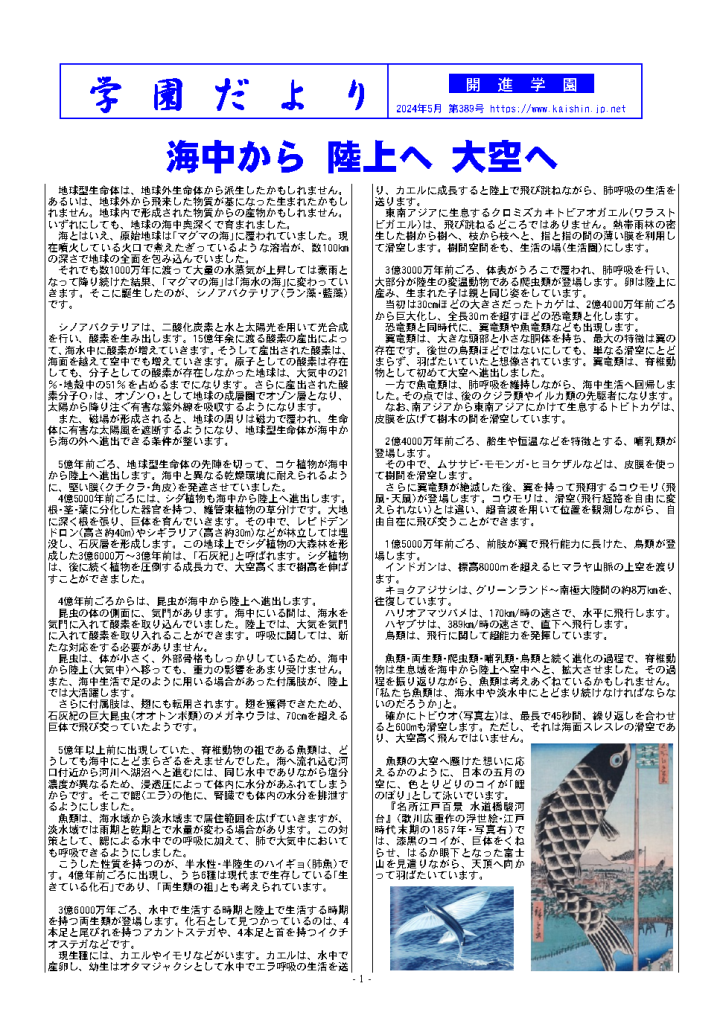
『地中海東岸地方 アラブ・ユダヤの垣根を越えて 』 12月の開進学園だより
『 平方根(非循環無限小数)の存在 』 9月の開進学園だより
![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
二十四節気で、「小満」の次に来るのは、「芒種」です。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
魚類の中で、最長で45秒間、繰り返しを合計して600mも滑空するのは、何でしょう。
夢を実現する学習塾 開 進 学 園
ホームページ
