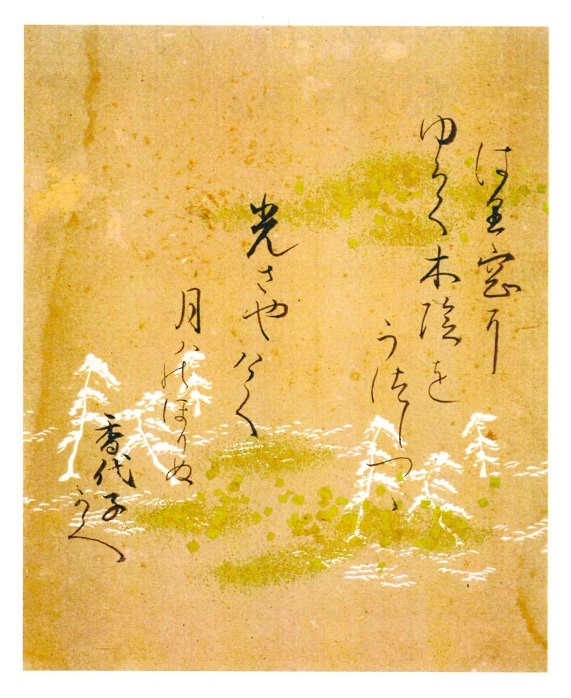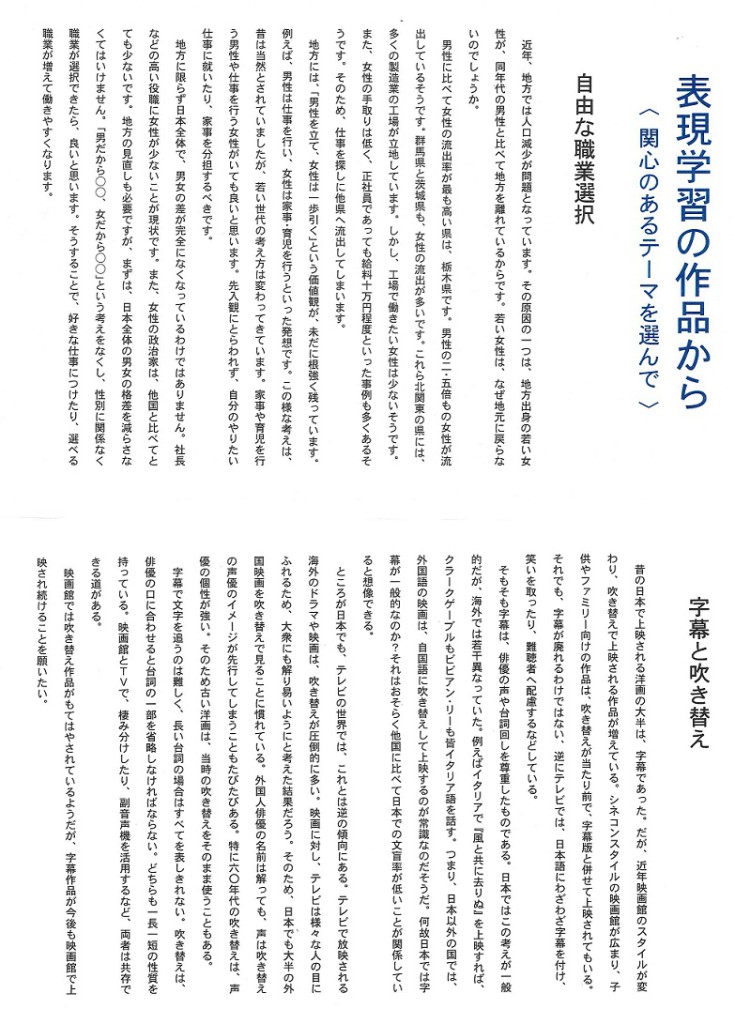白米の千枚田を後にして、国道249号線を日本海沿いに西下すると、輪島の街に入ります。
夕餉には素敵な割烹で「かますの焼き魚」などを頂きながら、英気を養います。
翌朝に出かけたのは、古い歴史を持つ「輪島の朝市」です。
「輪島の朝市」が始まったのは、800年ごろ(平安時代の初期)です。
神社の祭礼に際して、水産物や農産物などを持ち寄って販売し始めたようです。
やがて、12日目ごとに開かれるようになった市は、10日目ごとに開かれるようになり、一月に六回開かれるようにと、間隔が短くなっていきます。
戦後には、夕市も開かれます。
朝市と夕市とお斉市の三者を合わせて、「輪島の市」と呼ばれるようになります。
1970年からは、毎日8時から12時まで車両の通行が禁止されます。
それに伴い、輪島を訪れる観光客は、1965年の約35万人から、1970年の約115万人へと、急増します。
地域住民の生活を支える朝市は、観光客をも含めた朝市へ、拡大します。
この1200年を超える歴史を持つ「輪島の朝市」へ、2024年1月1日に巨大地震が襲いかかります。
建物の倒壊に加え、大規模火災が発生します。
大規模火災は、1月1日17時ごろから1月6日17時ごろまで、五日間にも渡り、約240棟を焼き尽くしました。
「輪島の朝市」は、残念ながら、現在休業中です。
それでも、全国各地で「出張輪島朝市」を開催しようと、奮闘されています。

〈 新潟県最西端・富山県との境界 〉本州の海岸線一周 その56
![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
日本の人口は、カラーリット・ヌナート(グリーンランド)の人口の、約2210倍です。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
日本の三大朝市は、どこでしょう。
夢を実現する学習塾 開 進 学 園
ホームページ