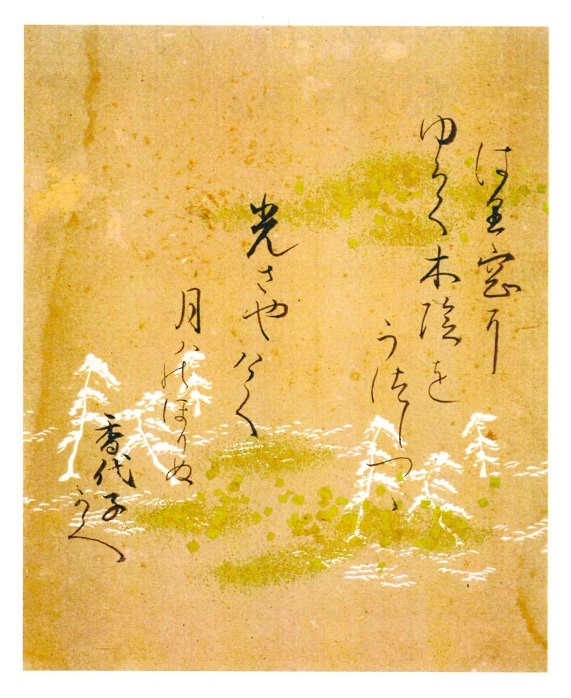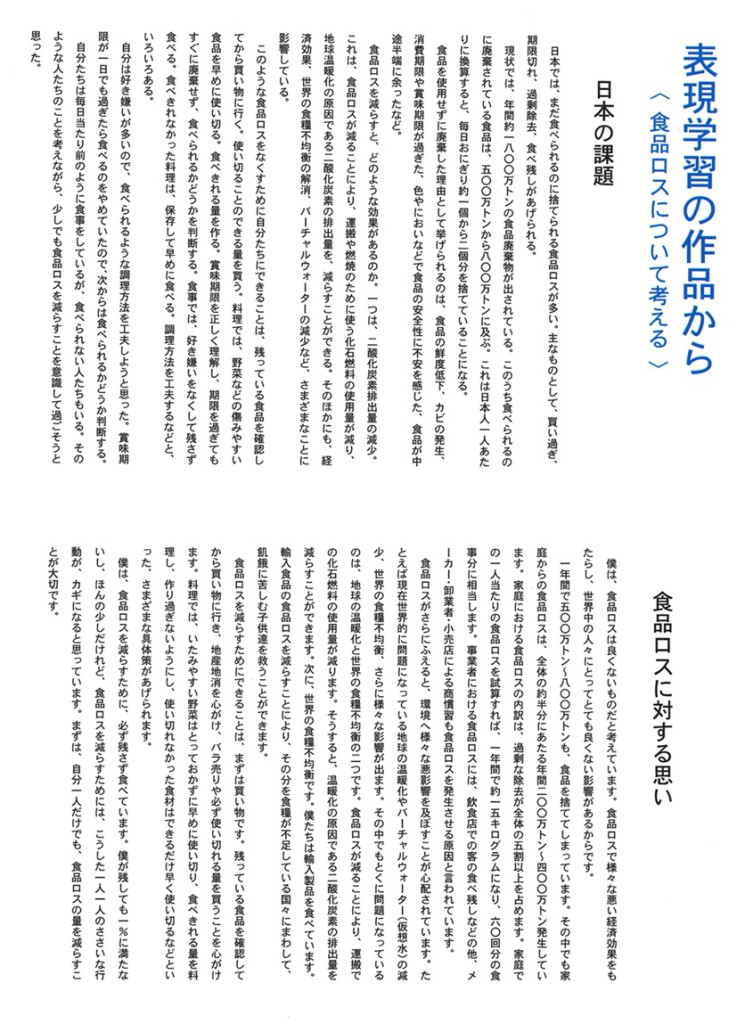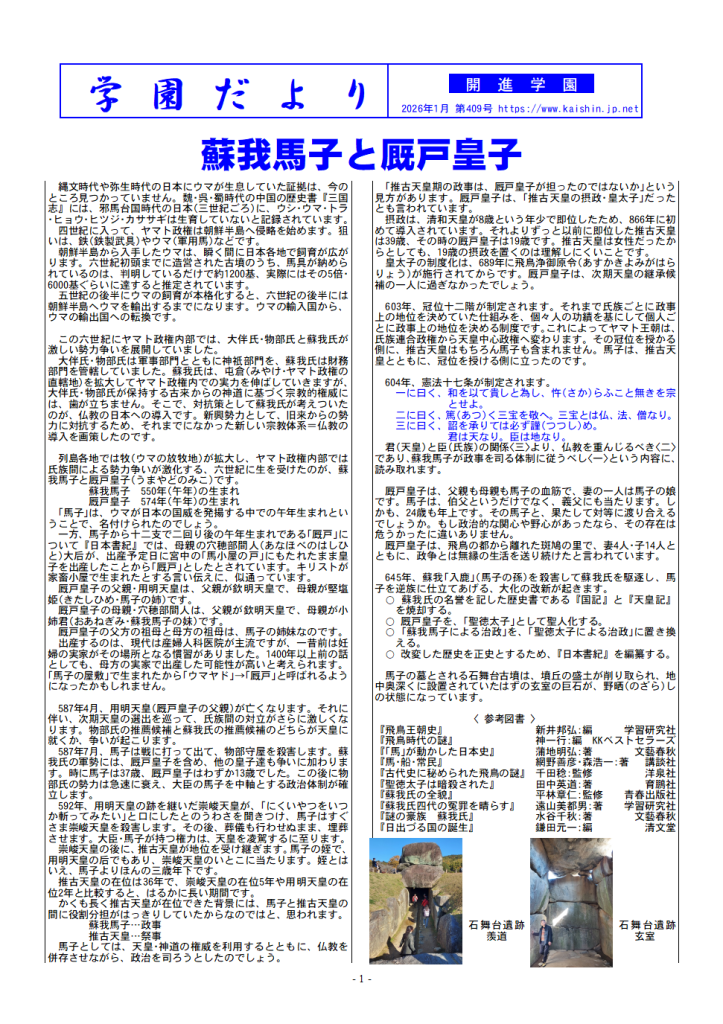茶の湯を専用に行う場所は、「茶室」と呼ばれています。
ただし、「茶室」という名称が用いられるようになったのは、江戸時代も後半からのようです。
「茶室」の代わりに、「茶の間」「茶屋」「茶席」「数寄屋」など、様々に呼ばれていました。
それらの中で、最も多く用いられた呼び方は、「座敷」です。
「座敷」とは、「座」が敷き詰められている部屋です。
「座」とは、「畳」のことです。
「大広間」や「書院の間」のように、「畳」が敷き詰められているのは、征夷大将軍などが利用する特別な部屋です。
当時は、武士にしろ、商人にしろ、「畳」を敷き詰められるほどの経済力に達していません。
板の間に「畳」を数枚置いて、座る席にしていました。
それゆえ、狭いとしても、「畳」を敷き詰めた「茶室」は、文字通り「座敷」でした。
< つづく >

![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
「静寂」は、「せいじゃく」「せいせき」「しじま」と、読みます。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
「茶室」において、主人と客人の関係を表す四字熟語は、何でしょう。