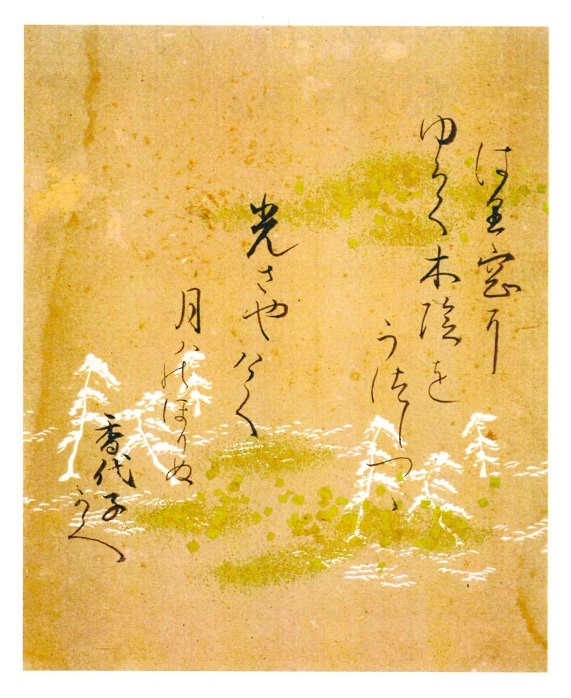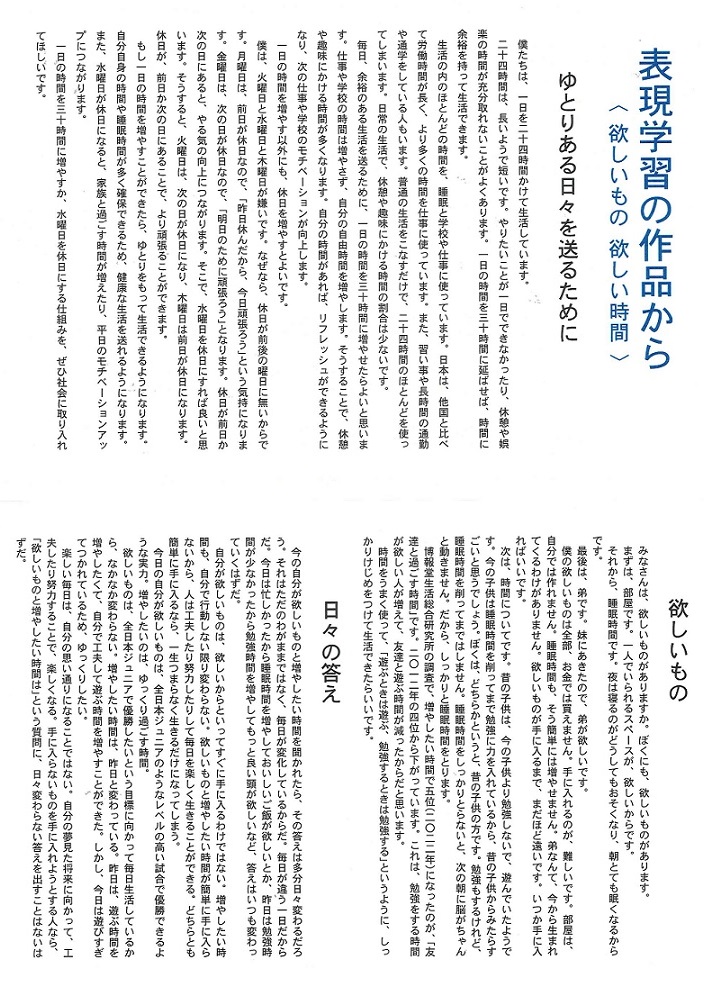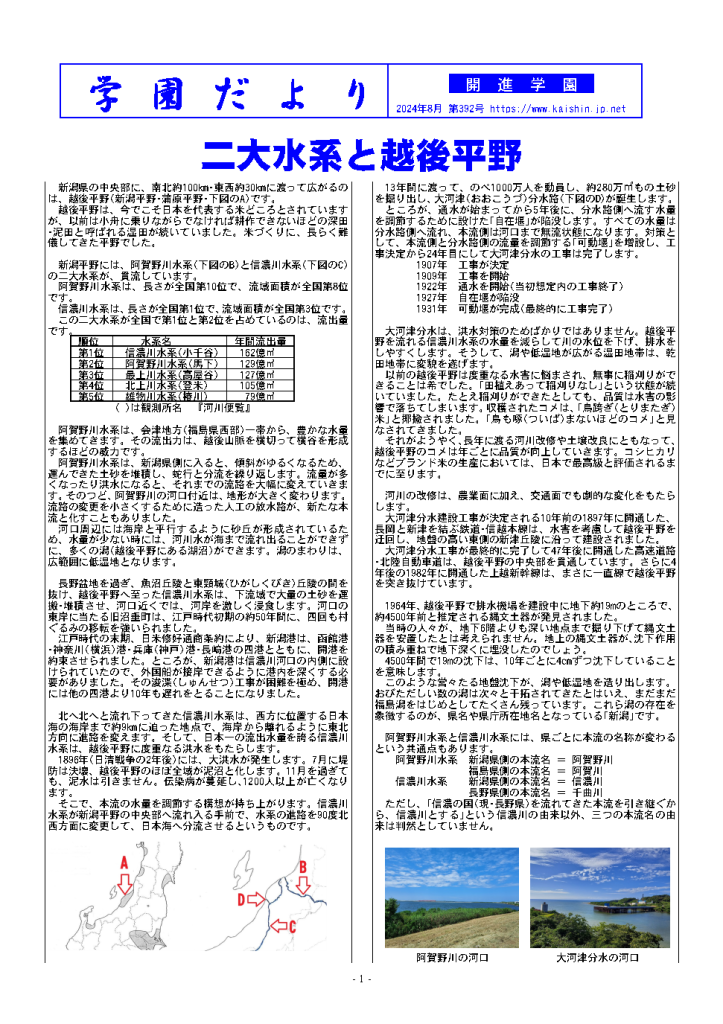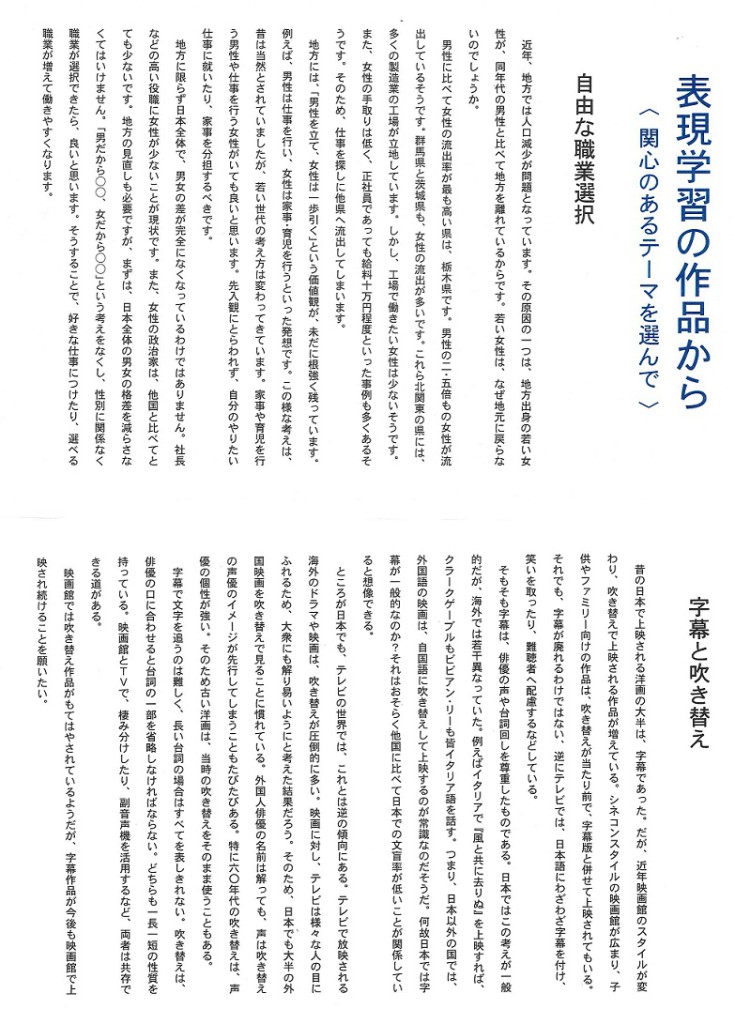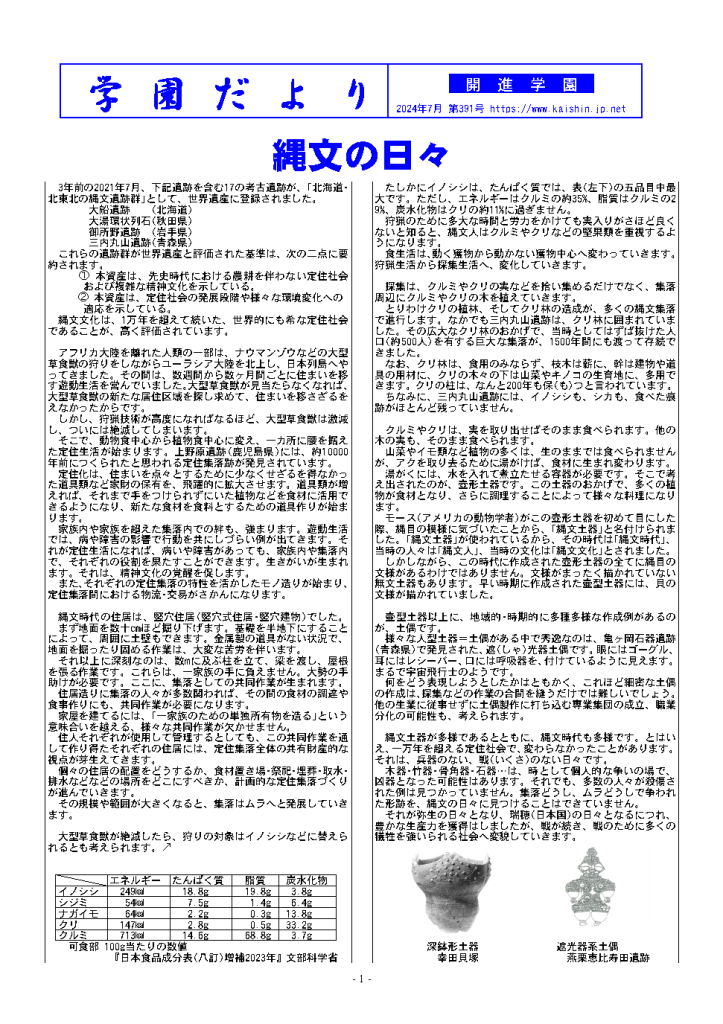開進学園叢書・歌集『香る代に』( 二瓶カヨ子 作 千葉日報社 )から、〈 せせらぎ 〉に因んだ短歌を三首紹介します。
さらさらと絶えず流るるせせらぎの
ほとりにありて独り物思ふ
せせらぎの音のかそけきこの夕べ
薄の穂末星は輝く
山里の木立の小舎に君と共に
語り合ひけりせせらぎ清く
〈 面影 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 兄君 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 花の春 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 雪 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 笑う 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
縄文海進のころ山麓までが海で、「着く波」と呼ばれたのが基になった山の名前は、筑波山です。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
8月28日=太陽太陰暦で七月二十五日(731年)、次の歌を残して亡くなったのは誰でしょう。
わが苑に梅の花散る久方の
天より雪の流れくるかも
夢を実現する学習塾 開 進 学 園
ホームページ