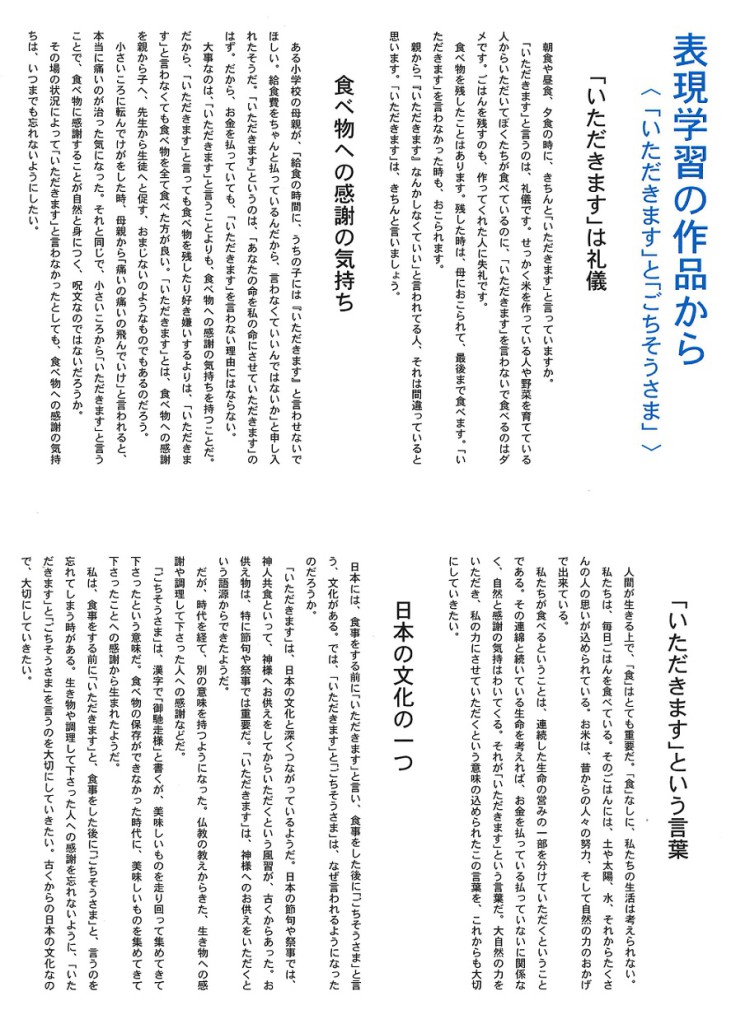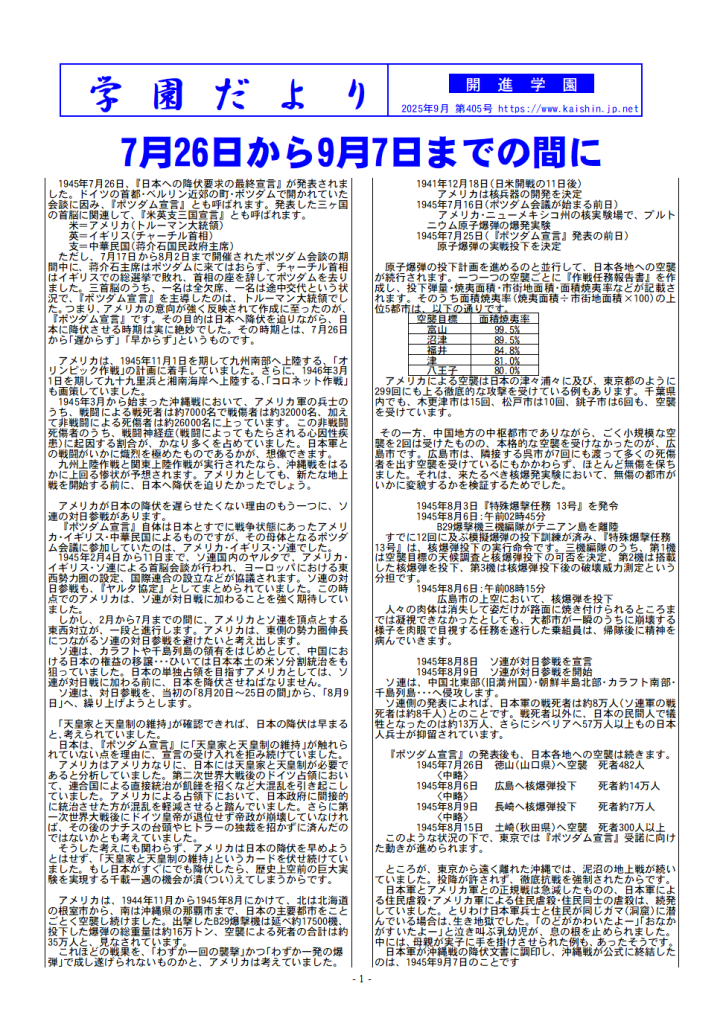津田沼駅のホームには、視覚障害者誘導用ブロックと同じ黄色ながら幅は狭く45度交差した破線が、引かれています。
黄色い破線の左側には「習志野市」と、黄色い破線の右側には「船橋市」と、表示されています。
黄色い破線は、「習志野市」と「船橋市」の境界線です。
1889年、五つの地区が合併し、そのうち谷津村から[津]を、久々田村から「田」を、鷺沼村から[沼]を、一字ずつ採って「津田沼村」が発足します。
1894年、市川~佐倉間に、総武鉄道が開通します。
日清戦争が始まった年です。
翌年の1895年に、津田沼駅が開業します。
津田沼駅の近くには、陸軍の演習場や鉄道連隊の施設などが並び、「軍都」ないし「軍郷」とも呼ばれるようになります。
戦後になると、演習場は住宅地に、軍の施設は大学のキャンパスなどになり、駅前は一大商業地へと変貌をとげます。
1954年、村制から町制へ移行していた「津田沼町」は、千葉市の西部地区を編入して「習志野市」となります。
津田沼駅は、ホームも、駅周辺商業地も、「習志野市」と「船橋市」に二分されながら、境界を感じさせません。
開業日は9月21日、今年で130周年を迎えました。
![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
「関彦橋」は、「かんげんきょう」です。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
大船駅は、何市と何市に跨っているでしょう。