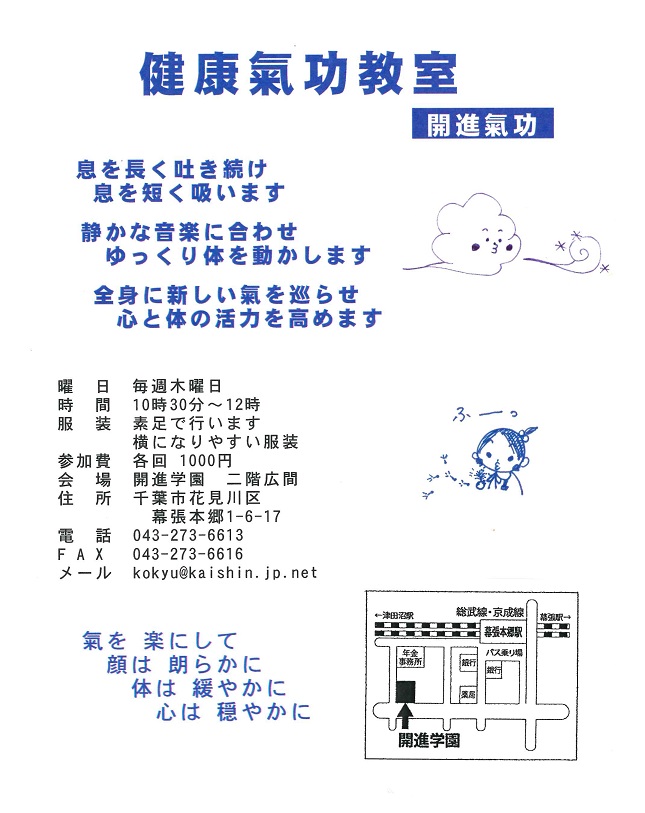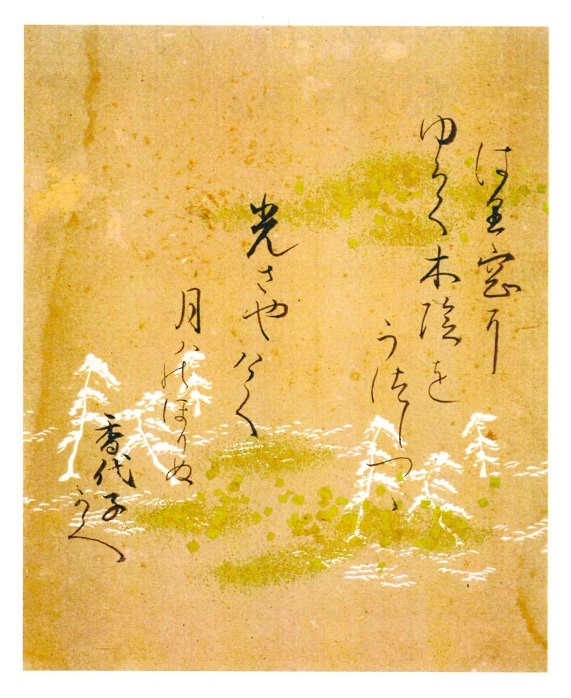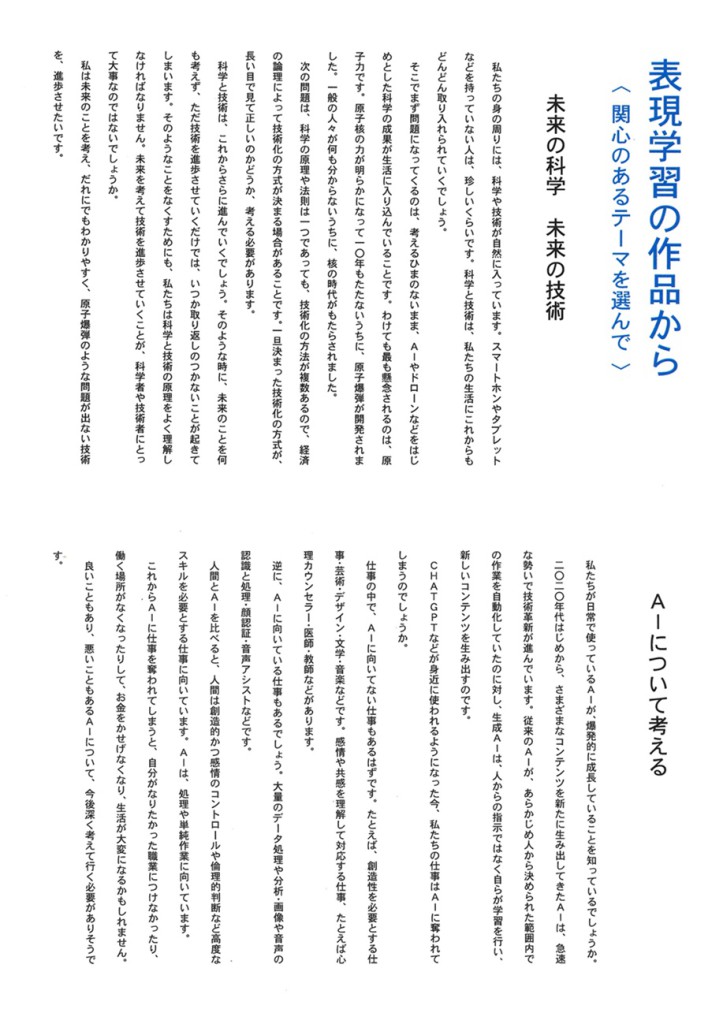「始功第十七:両腕を頭上に伸ばして、手指の開閉」と、「始功第十八:開脚長座で前屈」の続きです。
始功の調べに合わせ、呼吸を重ねながら、体を動かします。
始功第十九は、「立位・両脚屈折」です。
頭・背筋・腰・太腿を、畳の面と垂直にします。
両足は、肩幅に開きます。
以後、踵は畳面から離し続けます。
息を吐きながら、膝を曲げていきます。
頭・背筋・腰は、畳面に垂直のままです。
ふくらはぎと太腿が接するまで、膝を曲げます。
息を吐きながら、ゆっくりと、ゆっくりと、行います。
ふくらはぎと太腿が接したら、両脚を畳の面と垂直に戻します。
短く息を吸いながら、迅速に行います。
合わせて六回です。 < つづく >
< 健康気功教室 >
と き 毎週木曜日
10時30分~12時
ところ 開進学園 二階の広間
電 話 043-273-6613
メール kokyu@kaishin.jp.net