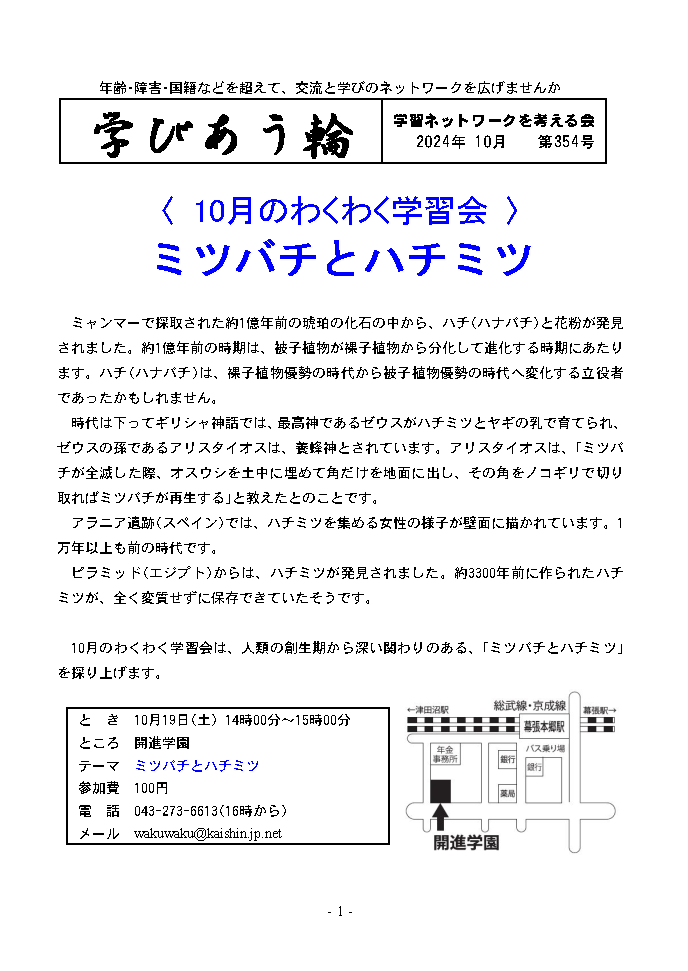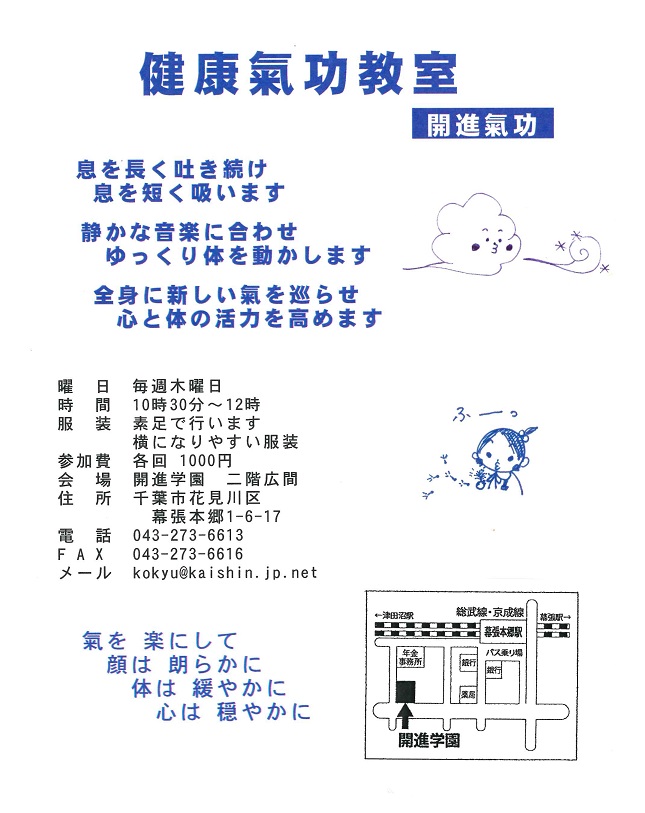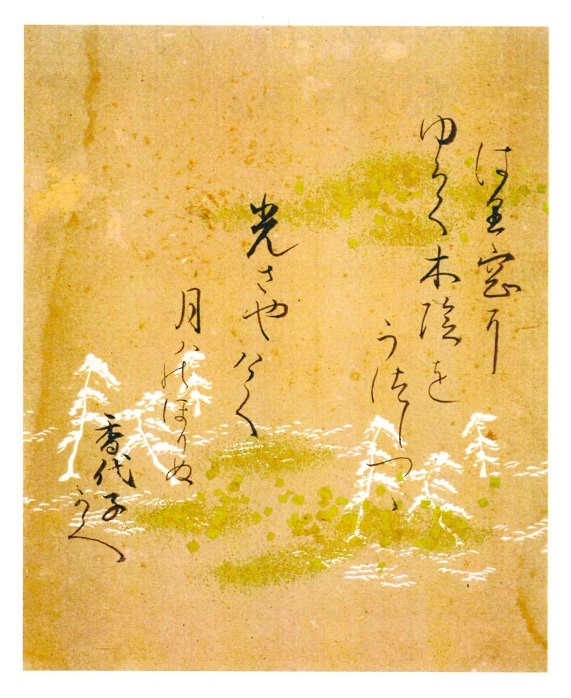東西に長い湾口を持つ若狭湾の東端部に、若狭湾の支湾=敦賀湾があります。
その敦賀湾の西側に突き出ているのが、敦賀半島です。
湾奥にある敦賀港にとっては、北西の季節風から守ってくれる、天然の防波堤となっています。
敦賀半島の西岸を進むと、車で行けるのは北端の集落・立石までです。
立石集落から立石岬灯台までは、歩いて数100mほどだそうですが、草が生い茂っていて、草刈り機なしで進むのは断念せざるをえません。
立石岬灯台は、日本海側で二番目に建設された、古い歴史を持っています。
敦賀市のシンボルとなっていて、敦賀市の市章にもデザインされています。
敦賀半島の北西端には敦賀原子力発電所が、敦賀半島の北東端には美浜原子力発電所が、あります。
さらに実験炉・もんじゅなども加わり、敦賀半島は「原発銀座」と呼ばれています。
原子力発電所の密集に加えて、活断層との関係も問題になっています。
敦賀原子力発電所は浦底断層の真上に立地し、美浜原子力発電所は白木・丹生断層のすぐ傍に立地しています。
敦賀半島では、「活断層銀座」と「原発銀座」が同居しています。

![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
体内に入ったペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の95%を排出するのに、約40年かかります。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
日本海側で二番目という古い歴史を持つ立石岬灯台は、何年に建設されたでしょう。
夢を実現する学習塾 開 進 学 園
ホームページ