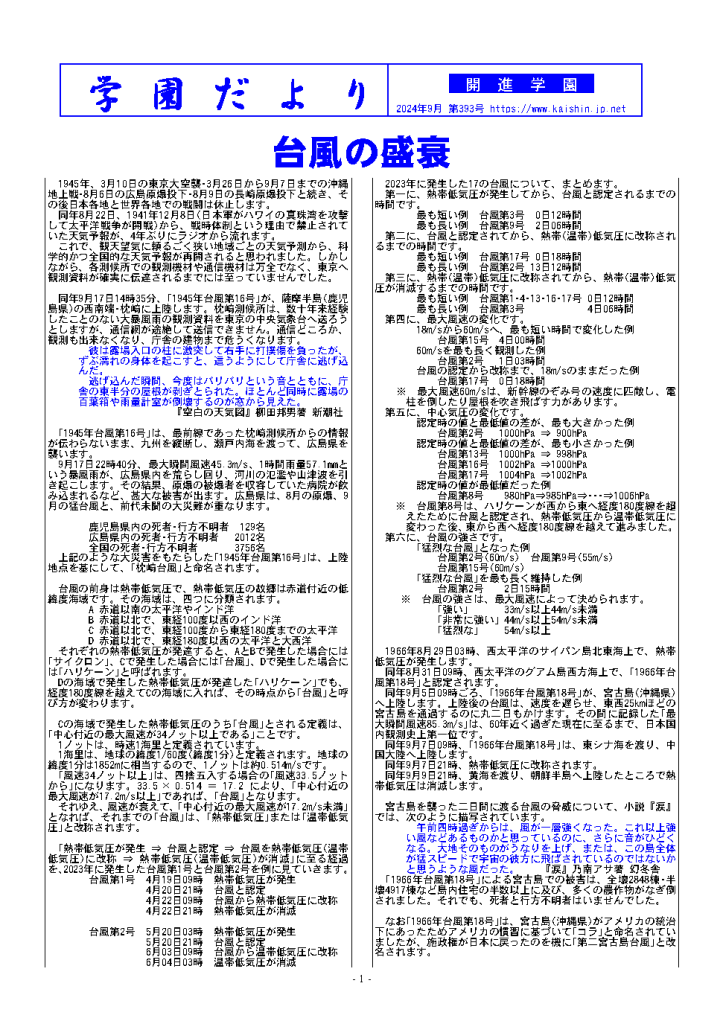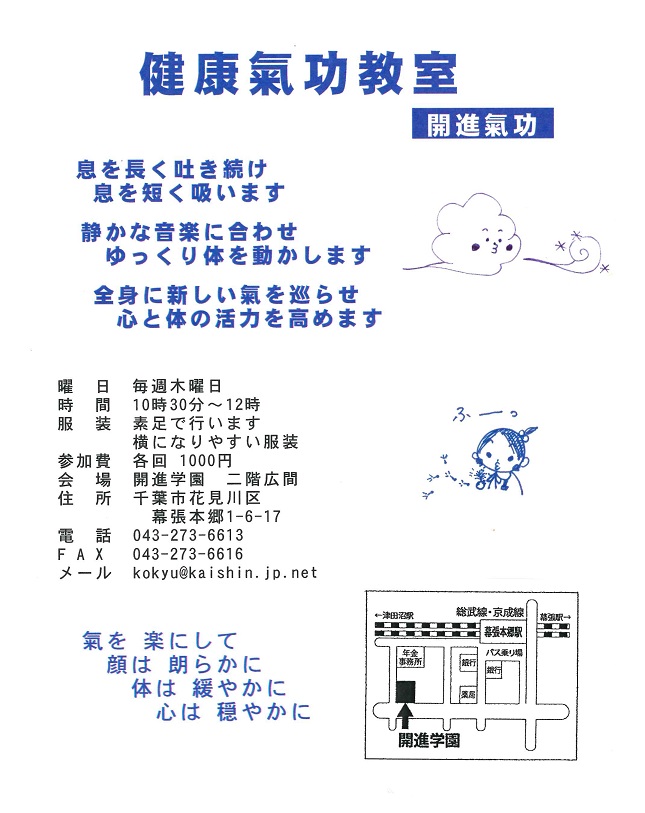コーカソイドは、西方へ進み、ヨーロッパに至ります。
その中の一部は、北ヨーロッパからアイスランドへ進みます。
そのまた一部は、カラーリット・ヌナート(グリーンランド)へ渡って行きます。
モンゴロイドは、東方へ進み、アジア各地へ移住しながら、生活技術を革新していきます。
中でも細石器の製作術を身に付けたことで、軽くて強力な槍や矢を創り出します。
狩猟技術の進歩は、豊かな食生活をもたらすばかりではありません。
皮革は、温かな衣服・寝具・家屋の材料になります。
集団で狩猟すれば、互いのコミュニケーション力も、言語能力も、高まります。
モンゴロイドのうち狩猟用具や寒さに耐える生活用具を携えた集団は、北方へ向かいます。
北方の大地には、大型哺乳類がたくさん生息していたからです。
今から2~3万年前ごろ、モンゴロイドは、北緯50度線を越え、シベリアにまで生活圏を拡大します。 < つづく >

東へ進むモンゴロイド・西へ進むコーカソイド その1
〈 大陸と大陸の裂け目 〉メルボルン紀行 その11
武器も基地も無い平和 スヴァールバル諸島とオーランド諸島 その16
〈 レンタカーによるタスマニア島南北縦断の旅 〉タスマニア紀行 その八
![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
「1966年台風第18号」は、上陸地点に因んで「第二宮古島台風」と命名されています。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
ヌーク(カラーリット・ヌナート)における最暖月=7月の平均最低気温は、何度でしょう。
A +15℃
B + 5℃
C - 5℃
D -15℃
夢を実現する学習塾 開 進 学 園
ホームページ