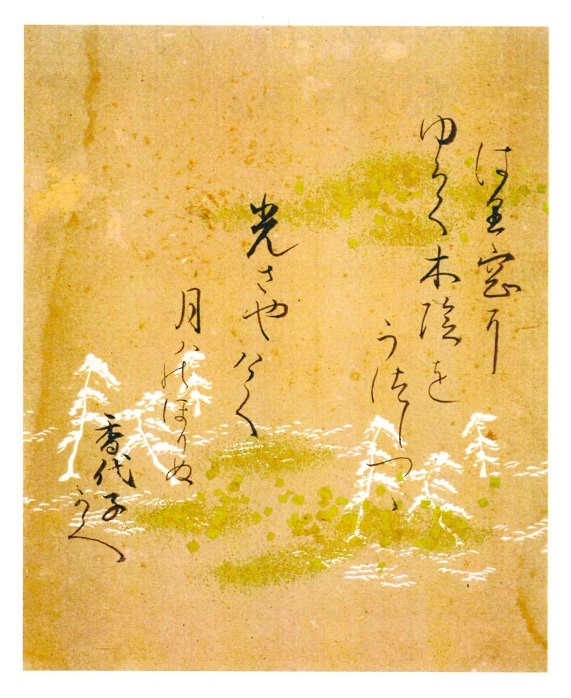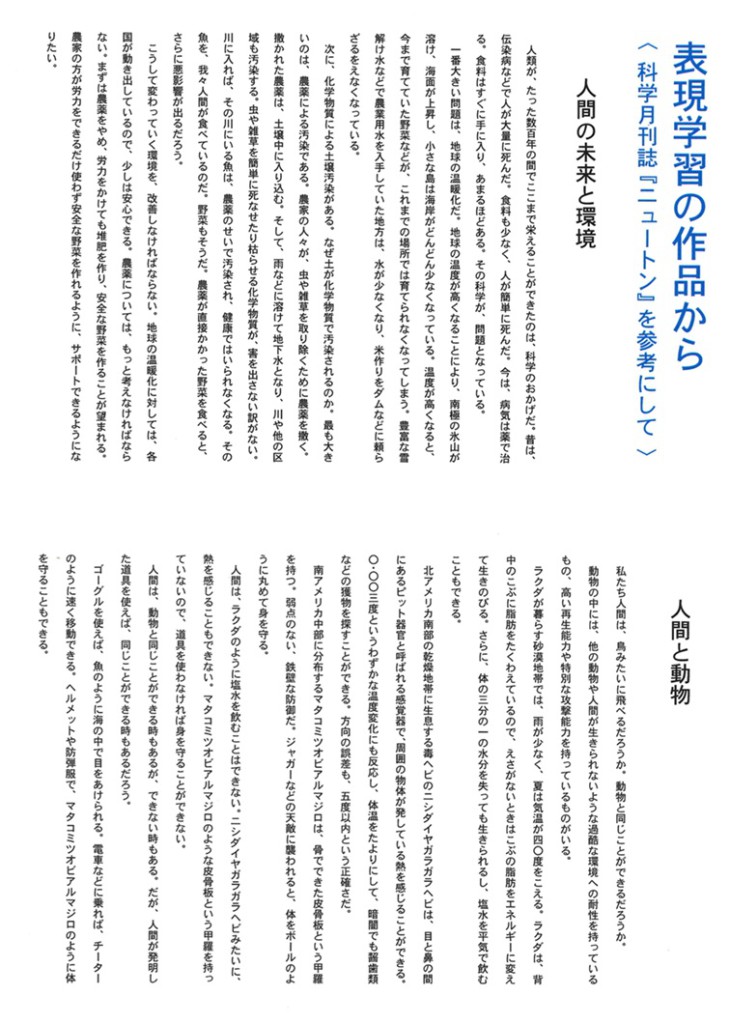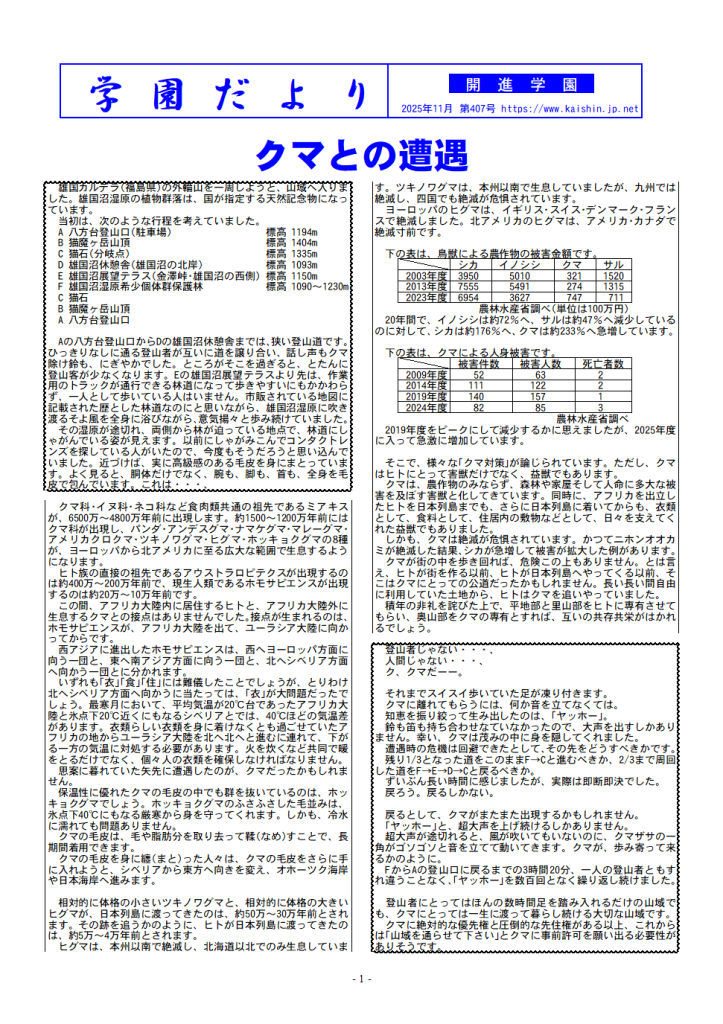開進学園叢書・歌集『香る代に』( 二瓶カヨ子 作 千葉日報社 )から、〈 ひかり 〉に因んだ短歌を三首紹介します。
ほほゑめる人の美ししづかなる
心のひかり面にうつりて
ひたすらに運命のままに生き抜かん
望みかがやく光たどりて
限りなき恵みに栄えよゆく道の
永遠に輝く光目ざして
〈 心 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 吾 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 息吹 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
〈 燃える 〉
開進学園叢書・歌集『香る代に』から
![]() 前回の問題 解答
前回の問題 解答![]()
石炭記念館の展望台は、宇部市の炭鉱の竪坑櫓を再利用しています。
![]() 今日の問題
今日の問題![]()
1985年11月25日、中高年齢層に関する新名称公募委員会は、50代や60代にふさわしい名称に、何を選定したでしょうか。